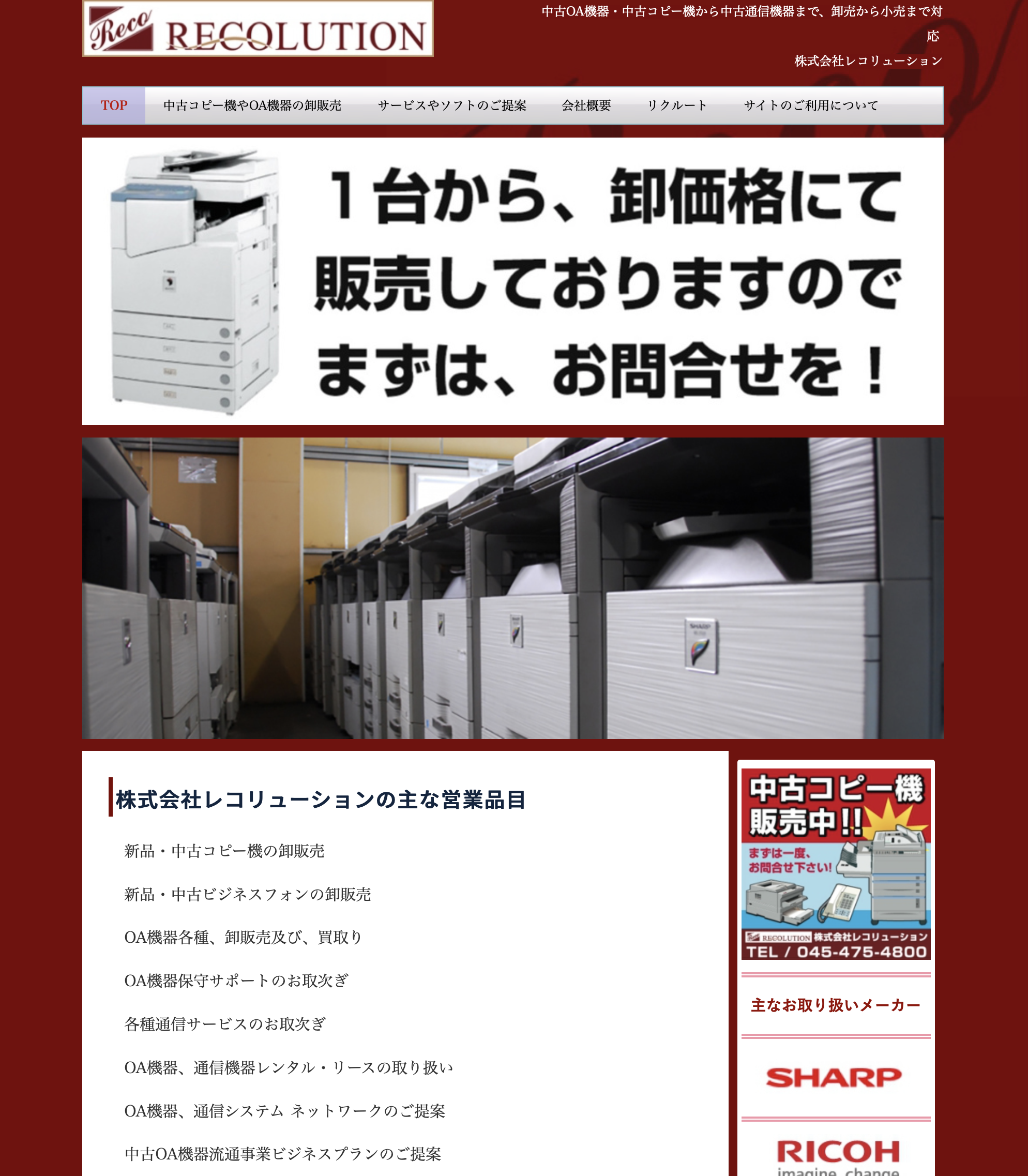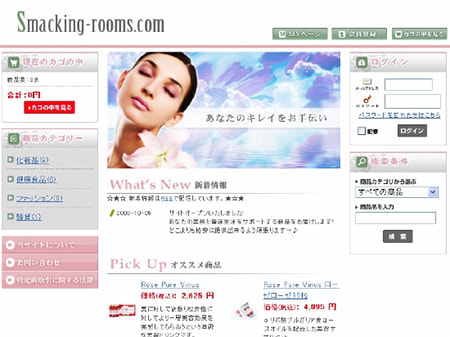WEB CONTENTS, SOCIAL MEDIA
ホームページやSNSでの品格
ファンづくりを目指すブランディングを、ウェブメディアに限定すると、アプローチの初めはSEO対策に強く、誰もが共有しやすい、独自のホームページをしっかり整えて、ターゲットユーザーに丁寧に情報発信する事が優先されますが、最近のホームページ作りは、広告代理店、システム会社やウェブ制作会社などで、サイト枠やバナー枠を買い、作業アプリ利用料や、サイト立ち上げ代行を依頼をする方が多くなっています。
これでは、どんなに小規模であっても、ホームページを運営する上で本当に必要な、コンセプト作り、アプローチの構成、訴求の為のデザイン、プロモーション計画と来店時の対応までを加味した、MD計画を立てて進める事ができません。
結果、苦労の割に効果が薄いモノになる場合があります。せっかくホームページを創るのであれば、ターゲットに対するアプローチの専門性、ユーザーがサイトの発見から来店まで誘引する企画構成、ブランド感を伝えるためのデザインまで、しっかり決めた上で進めていかないと、側は立派な様に見えても効果が得られないという事になってしまいます。
側の体裁の前に、運営管理をプロモーション目線でフォローアップし計画する事が重要であり、これは最初の立ち上げ時の企画に仕込んでいきます。システム会社などはラニング重視もありますが、後からプラスしていくサイト作りが目立ち、計画的なMD戦略に基づいているものが少なく、プロモーションの視点では弱く、それこそ行政などは、URLが驚くほど長いものも多く見受けられるのは、この長期的な予測と計画ができていないからでしょう。
私たちは、数ページのサイトであっても、この様な非効率さを防ぎ、最適なブランディングが行える様に、プロモーションデザインという武器を通して、MD計画をしっかりと立てて情報を精査し、長期的に活きるサイト作りを行います。
また現在は、残念ながら、「目立つ」、「見やすい」と謳う、ひな形の利用がネットでも印刷でも主流化しています。以前、「◎◎の品格」という言葉が流行りましたが、ブランド感に合う品格/品質を持った(大衆的という品質であっても)ホームページは、この様なひな形では作れません。時に私たちは、オリジナリティを検討するために、必要であればスケッチでホームページやチラシを描きおこします。それが、オリジナリティを生み出す正しいアプローチだからに他なりません。
例えば、30席未満の飲食店の場合、コンセプト決めや、イメージヴィジュアルの設定は勿論のこと、ファン化目標はどうするか?などもポイントに置きます。現状の利用者の月間数値、席稼働率やご愛顧頂いているお客様指数や売上比も検討し、新規開拓先かリピート重視かなど、営業方針に合わせながら、キャパに合わせた費用対効果の得られる範囲を検討していきます。
ファン数は、必ずしも来客実数や売上と一致はしませんが、多くのファンを持つという事は、今の様な未曾有の状況下で強いという面もあります。だからこそ、ブランディング面でみれば、最新商品情報などのニュース配信を、独自のホームページで小まめに行うのが一番効果的です。
勿論、一定数のファンがすでにいる場合、InstagramやFacebook、Twitter、YouTube等のウェブアプリなどソーシャルメディアを使う方法もあります。但し、これらは使い方や見せ方を、本家のホームページや店舗のブランド感に合わせて、イメージの価値を共有していくものです。すでに顧客がついていればそれだけでも良いかも知れませんが、「おもてなし方」や「付加価値」が明確な本家サイトがあり、フォローアップとしての活用が適しています。それこそ、ソーシャルメディアで偶然初めて訪れた時、TwitterやInstagramが休業の告知だけであったりしたら、行きたくなるでしょうか?
ホームページは、余暇の楽しみを検索されている方と初めて出逢う、まさにファン化のキッカケのチャンスです。ソーシャルメディア系は偶然も多いからこそ、写真1枚も、ブランド感に合わせてアプローチしたり、コメント付けたりしていくと、よりよい運営に繋がりす。
現在、ホームページやSNSで悩んでいる方、ホームページ作りにおける最初の入口が違っただけ、最初の依頼先の得意不得意が見極められていなかったという場合もあります。また、サイトに掲載するのは店舗案内なのか、それとも、メニュー表、日々の情報、コンセプトやバックボーンを伝えるのかなど、絞るか広げるか、お店に来店された時と同じ様に感じてもらえたらなどもあるかも知れません。新規で作ろう、改善策を検討してみたいなどの疑問から、簡単な修正や取組に対するワンポイントアドバイスのみも対応しております。まずは、お気軽にお問合せ下さい。
ブランド感を伝える最適な手段
しっかりと情報発信をしながら安定化を図る事で、お申込や予約フォームの流入も本サイトから一番多く見込めて、効率的なブランディングとプロモーションを維持管理出来ます。
■サイト作りの必須要素『3とめ印』
『目にとめ、手をとめ、記憶にとどめる』
1)どのようにして目にとめさせるか
2)いかに手をとめさせるか
3)何を記憶にとどめさせるか
ターゲットユーザーはどこにいるか?
企画やコンテンツとデザインの整合性は?
差別化を図る要素は明確になっているか?
流行に流されない計画は立てているか?
扱いやすさや分かり易さ(UI)の取組は?
地域密着の都区内や神奈川県内から、全国まで対応しています。
手軽なツールこそ丁寧に差別化しよう!
■ソーシャルメディアの使い方
ソーシャルメディアは、プロバイダーが提供する日記形式のブログから始まり、短文のテキスト投稿のTwitter、プロフィールツールとしての当初は自分のページをカスタマイズも出来たFacebookと、発信内容に合わせて選べました。
その後、国産SNSとしてmixiが、ガラケーでも使える利便性から広がり、今では様々な枝分かれをし、スマホ向けにアプリ化されたものが主流になっています。
Facebookはカスタマイズも出来なくなり、昨年はついにPCライクに階層化されていた仕様が、スマホ向けに大幅変更し、トップページに全てメニュー化され、プロモーションで使いにくくなってしまたり、Instagramも時系列表示が無くなってから、広告が増え、見たい情報が即座には拾えず、こちらもリアルタイム情報向きではなくなってしまいました。Twitterはリアルタイムな情報発信では若い人のスタンダードになり、Twitterが始まった頃のユーザーとは使い方も変わってきています。
ソーシャルメディアの懸念点は、自分でゼロから作るホームページと違い、この様に仕様変更が突然起きたり、Yahoo!ブログなどの様にサービスが無くなる場合もあります。そういう点からSNSは、その時限りと割り切って、ホームページを活かせる形で使うのが良いでしょう。
■方向性を決めていく
例えば、YouTubeでYouTuberを目指さなくても、季節ごとに動画を撮影してホームページに埋め込んでいくという使い方も出来ます。肝心なのは、ソーシャルメディアもホームページ同様、ブランディングをしていくことです。これは、統一感というのもありますが、リアルな環境(店舗や売場、商品、サービス)と同じ様に、テキストや写真、映像を扱う事が大切です。
実際は、アップするだけでも精一杯という感じの企業や店舗のSNSもまだ多いのが現状で(勿論、ブランディングとしてSNSを利用していない企業や店舗もあるわけですが)、写真、文章のプロとは大きく差が開きます。
だからこそ、キャッチコピー、写真、テキスト文となるライティング、全体の構成、プロフィール情報などまで、プロフェッショナルな仕事を少しでも参考にしてアプローチをすると、競合との差を早く着けられ、その分、人の目に留まる機会が増えるでしょう。
下記では、最初に取り組みやすい写真から、インスタなどでも使われるスクエアな形を参考に、初歩的な留意点を書き出してみたのでご参照ください。













商いは「飽きないものを」とも言われます。SNSなどは特に、閲覧者を飽きさせないアプローチをどうしたら良いか、改善策を検討してみたいなど、セールスプロモーション目線で考えると疑問などあると思います。弊社ではワンポイントアドバイスなど、お気軽に受け付けていますので、まずはお問合せよりご相談ください。